NEWS
鋳物不良とは?
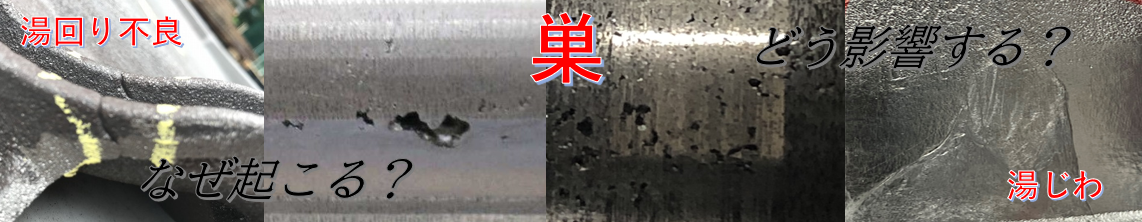
金属を型に流し込んで固める「鋳造(ちゅうぞう)」という技術。この過程では様々な条件が影響し、時に「不良品」となってしまうことがあります。その代表的な不良が、「巣(鬆、す)」と呼ばれるものです。
不良によって起きる問題
不良により、製品としての品質や機能に大きな問題が出ることがあります。たとえば…
・漏れが発生する
・形が不揃いになる
・歩留まりが悪くなる
・加工が無駄になる
・追加の加工が必要になる
・トラブル対応で手間がかかる
・納期に遅れが出る …etc
つまり、鋳物不良は製品の信頼性だけでなく、コストやスケジュールにも悪影響を与えることに繋がります。
不良の種類と原因
鋳物不良には、いくつかのタイプがあります。それぞれの原因を見てみましょう。

◆金属の性質による不良
・巣、鬆(ピンホール、潮吹き穴、引け巣など)
金属が固まるときにガスが発生し、空洞が出来てしまう現象。
・異物の混入(砂かみ、のろかみ)
型に使われる砂や金属のカスなどが混ざってしまう。
・湯じわ、湯紋(ゆもん)
金属の冷え方の違いで、表面にシワのような模様ができる。
・焼きつき、融合
高温の金属が型の砂とくっついてしまう
・表面の出っ張りや反り
金属が上手く流れなかったり、冷え方にムラがあると発生。
・鋳肌不良
表面がザラザラして仕上がりが悪くなる。
◆熱による不良
・高温割れ
熱のストレスで製品にヒビが入る。
・チル(白銑化)
一部が極端に硬くなり、加工しづらくなる。
◆形状による不良
・ミスマッチ、型ズレ
上下の型の位置がずれて、形が合わなくなる。
・中子ズレ、肉寄り、芯ズレ
型の中で中子がズレて(浮いて)しまい、厚みが偏る。
・湯回り不良
金属が隅々まで流れず、形が不完全に。
・寸法不良
設計と実際のサイズが合わない。
・割れ、欠け、打痕
鋳造後にぶつけたり、欠けたりして傷がつく。
対策については次回からご紹介いたします!
今回は、不良の種類と原因を大まかにご紹介しました。次回は、これらの不良を防ぐための具体的な対策について、分かりやすく解説していきます!